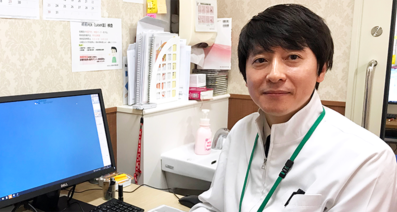
不正出血の原因検索をする場合や、子宮がん検診の結果説明において「子宮内膜増殖症」と診断されることがあります。子宮内膜増殖症には複数の種類があり、それぞれにリスクに違いがあるため、注意が必要です。この記事では、子宮内膜増殖症があると言われた方が知っておくべきことをまとめています。山王病院院長 堤治先生にうかがいました。
子宮内膜増殖症とは―その原因は?
正常の場合、子宮内膜は月経周期に伴って分厚く増殖し、月経時にはがれ落ちて出血します。下図の月経周期の表をご参照ください。

月経周期の表
さらに詳しく述べると、月経周期前半にはエストロゲンが分泌され、子宮内膜が増殖して厚くなります。この時期は子宮内膜周期の増殖期とも呼ばれます。月経周期後半には卵巣からプロゲステロンが分泌され、子宮内膜も増殖は停止し、分泌期に入ります。プロゲステロンには子宮内膜の増殖を抑える働きがあります。その抑制がかからないとき、子宮内膜の増殖が続き、場合によっては子宮内膜増殖症と呼ばれる状態に陥るのです。この結果、症状としては、不正性器出血、無排卵周期症などが見られます。
がんが発生する可能性がある
内膜を構成する細胞が正常でない場合を、「細胞異型がある」といいます。子宮内膜増殖症では正常な細胞が増殖する場合も多いのですが、「異型がある」というケースはより悪い「前がん状態」ということができます。つまり、異型があるかないかで癌化のしやすさが大きく異なってくるのです。
●異型なしの場合:癌化のリスクは小さく、癌への進行度は1〜3%
●異型ありの場合:癌化のリスクは大きく、癌への進行度は17〜50%
子宮内膜増殖症の治療は、上記2つのどちらであるかによって選択肢が変わってきます。
子宮内膜症との違いは?
子宮内膜症と子宮内膜増殖症は名前が似ていますが、全く異なる病気です。
子宮内膜症は子宮内膜組織が子宮以外の部分で増殖する病気です。まれにがん化して卵巣がんが発生することがありますが、基本的には良性疾患です。これに対して、子宮内膜増殖症は子宮内膜が子宮の中で増殖し、肥厚するものです。前項で述べたように、異型が強い場合は子宮内膜がんに移行する可能性が高まります。
子宮内膜増殖症の検査
子宮内膜増殖症の検査では、まずは超音波検査と細胞診、組織診などが行われます。ここで子宮内膜増殖症であるのかどうかを調べます。また、子宮内膜増殖症である場合、その状態を判断します。
経膣超音波検査
子宮内膜が厚くなっていないかを確認する検査です。
細胞診と組織診
・細胞診:子宮の内腔の表面を拭い異型があるのかどうかを見ます。
・組織診:子宮内膜の組織を直接採取して観察します。子宮内膜腺が過剰に増殖しているか、異型細胞があるかどうかを確認します。
以上のスクリーニング検査の結果異型がある場合は、次に述べる「内膜全面掻爬」という検査が必要となります。
内膜全面掻爬
異型がある場合、子宮体がんのリスクが大きく上昇するため、念のために子宮の全体を調べることにより、子宮体がんの有無を確認します。
これらの検査は、治療とも密接に関係しています。
子宮内膜増殖症の治療
スクリーニング検査において異型があったかどうかで更なる検査の必要性や治療の方針が大きく変わってきます。また、妊娠を希望するのか、しないのかによっても治療は大きく変わります。具体的には、下図のようなフローで治療がなされます。

山王病院(東京都) 名誉病院長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
堤 治 先生の所属医療機関
関連記事
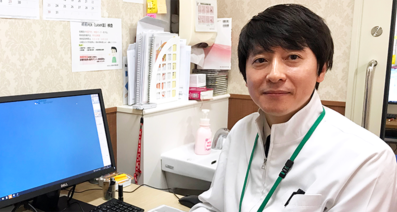

過多月経とはどんな状態?〜経血量が140ml以上の場合に診断される〜
関連の医療相談が19件あります
子宮摘出後の出血とおりもの
子宮内膜異形増殖症と診断され、12日前に腹腔鏡で子宮と卵巣を摘出しました。 手術直後はなかったのですが、一昨日からかなり少量ですが、出血とおりものがあります。おりものシートで十分足りる量ですが、これはよくあることでしょうか。 よろしくお願いします。
子宮卵巣摘出を進められた
3年位前に、不正出血があり個人の婦人科に診察をした所、内膜が厚いと言われたが、更年期障害だろうと言われる 昨年、健康診断で婦人科健診を受けた所、再検査の通知を頂き、別の病院で検査をしました 子宮内膜異形増殖症との診断 病理検査を3回して異形細胞がある。と 2回目は、内膜そうはをしました 子宮卵巣の摘出を進められたが、なかなか決心がつきません 子供は、いません 宜しくお願い致します
下腹部の痛みについて
多発性子宮筋腫があり10年以上経過観察の為定期的に受診しております。 一番大きいものは8.5センチあります。 最近では生理なのか不正出血なのか分からない出血が頻繁にあり貧血のため増血剤を飲んでいますがそれ以外の治療はしておりません。 主治医からは年齢的にも、もう少し様子を見ようと言われていました。 先日、子宮頸がんの検査をしたところ頸がんは異常なしでしたが特定不能な異型内膜細胞が見つかったとの事で体がん検査を受けました。 結果、体がんは異常なし。内膜増殖症と診断されました。 主治医からは内膜は厚いが超音波でも悪いものはなさそうだと言われ、3ヶ月後に体がん再検査をし結果によっては子宮内膜搔爬術を受けるように言われました。 これまで生理中やそれ以外でも腹痛は全くなく時々、排卵辺りに痛みがある程度でしたが、ここ数ヶ月は下腹部、腰痛が出血していない時に頻繁に起こります。主治医は排卵痛だと思うよ。との事でしたがこんなに頻繁に排卵痛が起こるのでしょうか。 また、排卵痛以外に何が考えられるでしょうか
子宮内膜増殖症と診断され体癌ではないかと不安で張り裂けそうです
4年半前に乳がんステージ1と診断され、片側の乳房全摘をしました。 ホルモン治療が開始され、ノルバディクスを5年間服用する治療をしております。 副作用を心配していましたが特にこれといった副作用の症状はなく元気に過ごしておりましたが、今年の5月に生理が1ヵ月止まらないので婦人科を受診したところ、子宮筋腫が降りてきてしまっているので筋腫をとらないと出血が止まらないと診断され、即子宮鏡下手術をしました。 しかしとってみたら、筋腫ではなく、良性の内膜ポリープでした。出血はおそらくこのポリープによるものではないかと言う診断でした。その後、不正出血もなく生理は順調にあります。 ただ、ノルバでホルモン治療をしているので体癌は3ヶ月ごとに見ていきましょうと言うことになり、8月の検査はクラス2で問題なし。 10月の検査がクラス3と出てしまいました。 より詳しい検査をしましょうと言うことになり、11月の頭に子宮内膜掻破の検査手術を一泊2日でして参りました。 この検査結果でもし異形ありと出た場合は、体癌に進行するから、子宮全摘の治療と言われ非常に不安になっております。ネットで調べると子宮内膜増殖症と言うとほとんどが体癌の前がん状態と言うように書かれていて、また癌告知をされ、今度は子宮全摘をし、最悪の場合、抗がん剤治療などが始まるのではないか、乳がんと体癌のダブルキャンサーになるのではないか、など、ものすごい不安になってしまいあと2週間結果が出るまで精神がもつかどうか自信がありません。 子宮内膜増殖症といわれ、掻破検査までしたら、ほとんどが体癌なのでしょうか? 主治医の見立てでは検査してみたら内膜がそんなに厚くなっていなかった、閉経前によく見られる症状だから、といわれましたが、一度乳がん告知され全摘をし、地獄のような思いをしているだけに不安でたまりません。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「子宮内膜増殖症」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。

