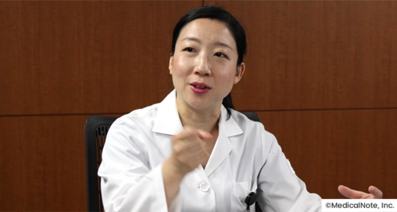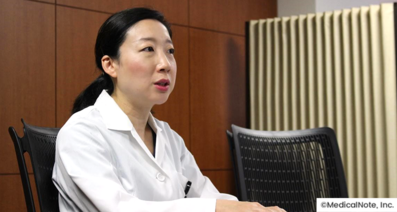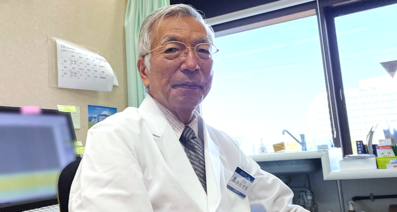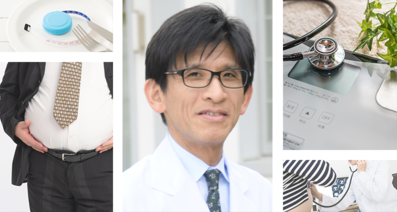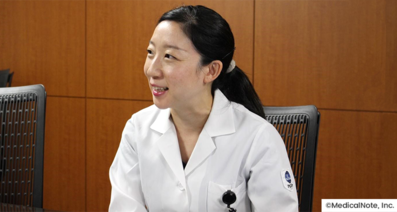
肥満症の治療とは? ~薬はあくまで補助的な役割で、食・運動習慣を改善することが大切~
肥満症とは、肥満(BMI 25以上)によって健康障害が生じていたり、健康障害のリスクが高くなっていたりする状態のことです。肥満そのものは病気ではありませんが、肥満症は治療が必要な病気として取り扱われます。肥満症について詳しくは「肥満症とはどんな病気?~肥満・メタボリックシンドロームとの違いや受診の目安~」を参照してください。
肥満症の治療は食習慣や運動習慣といった生活習慣の改善を基本として、症状が重い場合は薬物治療や外科治療が必要になることもあります。それでは、具体的にどのような治療を行うのでしょうか。
肥満症の治療方針
肥満症の治療は、肥満状態を改善することで肥満による健康障害を改善するため、または健康障害のリスクを減らすために行います。
主な治療方法としては、食事療法、運動療法、行動療法、薬物療法、外科療法の5種類が挙げられますが、肥満症は食や運動習慣の乱れから生じる病気であり、主に食べ過ぎや運動不足を改善することで改善・解消が期待できるとされています。薬物療法などはあくまで補助的な役割であり、食・運動習慣を改善することが大切です。
しかし、単に食べ過ぎないようにする、活動量を増やすといってもなかなか難しく、簡単にできるものではありません。
では、肥満症の方は治療を受けるにあたり、どう向き合っていけばよいのでしょうか。5つの治療法のポイントについて、鶴間かねしろ内科クリニック 院長 朝倉 太郎先生にお話を聞きました。
食事療法
肥満症では、体重を減少させるために食事療法が行われます。
“食事療法”というと、とても難しく感じるかもしれません。また、“我慢すること”が食事療法であるとネガティブな印象をお持ちの方も多いことでしょう。
簡単に言えば、1日の摂取エネルギー量を消費エネルギー量よりも少なくすれば体重は減ってくるわけです。いかにその状態を達成するか、食事で工夫するのが食事療法です。
まずは生活を分析してみましょう。なかなか体重が減らない方の中には、自身の食事量を自覚されていない方が多くいらっしゃいます。その中に減量の大きなヒントが隠れています。何気なく食べている習慣を変えること、調理法の工夫、食べ方の工夫など、“我慢すること”ではない食事療法があります。
食事の分析や提案は管理栄養士が担当します。生活習慣病外来や肥満外来には必ず管理栄養士がいますので相談をしてみてください。
取るべき栄養を意識する
これまでのお話と矛盾するようですが、一番大切なことは“食べること”です。
減量を始めた方の中には、とにかく減らせばよいと“サラダだけ”などの極端な食事療法をして、必要な栄養が不足してしまう方がいらっしゃいます。
特に“たんぱく質”が不足してしまっている方が多い印象があります。たんぱく質は筋肉、骨など身体を作る大切な栄養です。男性では 60~65 g/日、女性では 50~55 g/日が必要です。たんぱく質の多く含まれるものは肉、魚など“主菜”となるものです。肉、魚などの中には100 gあたり約20gのたんぱく質が含まれています。毎食となるとけっこう大変な量だと思いますが、1食につき100g(たんぱく質として20g)の主菜を取ることを意識してください。


*注:たんぱく質量は全て生の場合で計算
食習慣を見直す
“生活習慣”としての食事の見直しが大切です。月に1回の飲み会をやめてみるより、毎日の間食を見直してみること、毎食の主食の量を決めてみることなど、頻度の高い習慣を変えてみましょう。習慣の変更はリバウンドのない着実な減量につながります。
調理法を工夫する
同じ食べ物でも、揚げるよりも蒸したり、網焼きしたりする調理方法のほうが摂取カロリーを減らすことができます。
さらに、低カロリーでかみごたえがある食品(きのこや、こんにゃくなど)を取り入れることで、かむ回数が増えるため少ない量でも満足感を得ることができます。
食べ方の工夫をする
一口一口をよくかんで時間をかけて食べることで、いつもより早く満腹感を覚え、食べ過ぎを防ぐことができます。盛り付けるお皿を一回り小さくすることは、盛り付ける量を少なくすることにつながります。こういった工夫を取り入れてみましょう。
運動療法
運動療法とは、運動を定期的・規則的に行うことにより、体重の減少や肥満症による健康障害の改善を目指す治療方法です。
運動には有酸素運動とレジスタンス運動があります。有酸素運動はウォーキング、ジョギング、水泳など、息が上がるような状態を一定時間継続するものを指し、効率的なエネルギーの消費が期待できます。レジスタンス運動はいわゆる筋力トレーニングのことです。重りやチューブ、あるいは自分の体の重さを利用して負荷をかけ、筋力の増強を図ります。
いずれの運動も“正しい方法”で行うことが重要です。種目、頻度、強度、時間、各々にあったものを選びましょう。さらには“正しいフォーム”で行うことが重要です。自己流の運動はけがの元となります。特に肥満症の方は関節に障害を抱えている方も多くいらっしゃいます。今までに運動経験のない方は、まず専門家に相談することをおすすめします。肥満外来では医師だけでなく、理学療法士、健康運動指導士が担当します。
また、最近では YouTube などで運動を紹介する動画を利用している方も多くなってきました。動画に合わせて行うことで、正しい方法で行うことが期待できます。
運動の習慣化を
減量できないのは運動ができていないからだ、と考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、普段から忙しく仕事をしている方に痩せられるほどの運動をする時間があるでしょうか。
運動におけるエネルギー消費は、実はあまり多くありません。たとえば1時間速足で歩いたとしても、その消費カロリーは高々“ご飯1膳(150 g)分”、減少するのは“体脂肪35g程度”です(体重60kgの場合)。1回の運動で減量に至るような運動はありません。継続すること、つまりは運動も習慣化することで減量につながっていきます。わずか1日体脂肪35gの減少も1か月すれば1kgです。
日常の生活活動にも目を向けてみましょう。日常生活における活動もエネルギーを消費します。たとえば、屋内の掃除は散歩と同等にエネルギーを消費します。「毎日30分歩いている」という事実は頑張っている感じはしますが、ほかの時間はほとんど座っている、寝転がっているでは効果はいかほどでしょう。純粋な運動だけではなく、1日の活動量を見直してみてはいかがでしょうか。
通勤がよい運動になっている方も多いでしょう。車通勤を電車通勤にかえることで体重が減ってきた、というような例は多くあります。在宅勤務が増えて体重が増えがちである方も多いでしょう。通勤などの毎日行っている活動がエネルギー消費につながっている証拠だと思います。
さらに運動にはエネルギーの消費だけでなく、血圧や血糖値によい影響を与える急性効果があります。運動の効果は持続時間が限られています。効果を持続させるためには継続することが重要となります。

行動療法
体重のコントロールがうまくいっていない方には、程度の差こそあれ食行動に問題があります。その問題点の抽出と分析を行い、修正を加えていく過程が行動療法です。体重増加につながる行動を減らし、体重減少につながる行動を増やしていく“行動変容”により、リバウンドのない持続可能な減量に導きます。
ここでは主に食事、活動の日常生活を分析し、分析に基づいて対策を立てていきます。たとえば、1日4回体重を測り、グラフ化する手法があります。具体的には起床直後、朝食直後、夕食直後、就寝前の4回体重を測定してその都度グラフに記入し、とくに起床直後の体重で変化を見ていきます。起床直後以外の測定は生活習慣によっての変化を反映しやすい時間帯になっているので、生活習慣と体重増減が関連づけられることで体重が減らない原因を知り、食行動の是正とその継続につながっていくことが期待できます。
また、そのほかの測定は生活習慣によっての変化を反映しやすい時間帯です。生活習慣と体重増減が関連づけられることとなり、体重が減らない原因を知り、食行動の是正とその継続につながっていくことが期待できます。
これ以外にも、さまざまな手法があります。体重増加につながるの“くせ”を知り、体重減少につなげていくことがポイントです。
薬物療法
肥満症の薬物療法として手段は多くはありません。マジンドールは食欲を抑制し、減量へと導きます。しかし、マジンドールは依存性があることから対象となる患者さんがBMI35以上の高度肥満症の方に限られ、その服薬期間も最大で3か月までとなっています。
糖尿病治療薬の中には体重減少効果を示す薬剤があります。糖尿病合併肥満症例では大きな効果を発揮することが期待できます。
SGLT2阻害薬は尿の中に糖を排出させる薬剤です。血糖値を低下させるだけでなく、減量効果が知られています。臨床研究では平均で3 kg程度の減量が報告されています。
GLP-1受容体作動薬は注射薬でしたが、2021年に経口薬も発売されました。血糖効果作用だけでなく、胃の動きの抑制作用、食欲抑制作用を持つことから減量につながります。こちらも臨床研究では平均6 kgまでの減量が報告されています。注射は1日1〜2回のものから週1回のものまであります。副作用は嘔気、嘔吐、便秘など消化器症状がよくみられます。使用継続が困難な程度まで出現する方もいらっしゃいます。
肥満症治療薬の開発は現在も続いています。チルゼパチド、高用量のセマグルチドなど、後述する外科手術に匹敵するような結果を示す薬も発売が開始、または予定されています。今後さらに選択肢が増えていくことでしょう。
いずれの薬剤も減量、美容目的に不適切に使用されている例が散見されます。安全性を担保する意味でも、さらに効果を最大限発揮させる意味でも、使用に習熟した医師により処方されなければなりません。
外科療法
肥満症の外科療法とは、手術によって体重の増加を防ぐ治療方法です。
さまざまな術式が施行されていますが、日本で保険収載されているのは腹腔鏡下スリーブ状胃切除術です。食事療法や運動療法などがうまくいかないBMI 35以上の高度肥満症の方で、18〜65歳までの方に専門医が必要と判断した場合に行われます。この手術では腹腔鏡を用いて胃を大きく切除、その体積を1/10まで減少させます。食事摂取量の減少が期待でき、既存の内科的治療と比較して大きな減量効果が報告されています。
医師とよく話し合って治療を進める
肥満症は治療が必要な状態であり、医療的な介入の下で減量を進めていきます。治療の基本となる食事療法や運動療法はこれまでの生活習慣を変える治療であるため、長期的に維持する場合には根気強い取り組みが必要となります。
場合によっては減量治療と合併症の治療を同時に進めていかなければならないこともあるため、医師と治療計画についてよく話し合ったうえで治療を続けるようにしましょう。
神奈川県内科医学会 幹事、糖尿病対策委員、大和市医師会内科医会 会長、横浜市立大学医学部 臨床教授、東林間/鶴間 かねしろ内科クリニック 理事長、杏林堂クリニック 院長
鶴間かねしろ内科クリニック 院長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
関連の医療相談が15件あります
コレステロールの値の見方について
去年の健康診断でコレステロールがLDLが134でHDLが47でした。基準値内ですがネットで二つの比率が高いとリスクが上がると見て怖くなり最近、総コレステロールが204だったので縄跳びをしたり間食に気をつけたりしています。比率でみるものなのか何が基準なのか教えて下さい。後はどのような生活に気をつけれさま良いのでしょうか?
今年に入ってから動けない
もともと肥満で今年に入ってから腰や膝が痛くなり だるかったり生理もこなくなり 先程気づいたのですが足が凄く浮腫んでいて辛いです。 水分をかなりとり トイレの回数も多いです。 頭痛や目眩 立ちくらみや舌が腫れて痛いです。 立ったり座ったりするのも身体中が痛く 肥満外来をすすめられたこともありますが 身体中が痛く病院になかなか行けません。 やはり肥満外来に行った方がいいでしょうか? ネットで肥満外来を探しましたが私の住んでる県には無いようで困っています。
不安です。
体重が100kgあります。そのため高血圧と血糖値が高いなどいろいろあります。今から減量をすれば、糖尿病や狭心症などの病気を回避出来るでしょうか?
痩せたいです。
だんだん肥えてきたので、痩せたいです。お酒をやめると痩せるのかもしれませんが、なかなかやめられません。どうしたら良いでしょうか。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「肥満症」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。