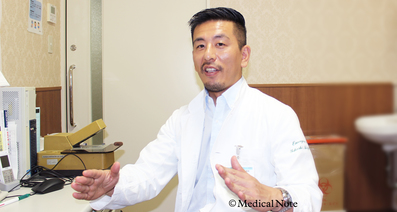
熱中症とは、暑さによって体温調節がうまくできなくなることよってさまざまな症状が現れる病気です。特に子どもは体温の調節機能が未発達であるため、自分で体調の変化に気づけないことから熱中症にかかりやすいといわれています。
今回は子どもが熱中症にかかりやすい理由や熱中症の予防方法、熱中症を疑う症状が現れたときの対応などについて、あいち小児保健医療総合センター 救急科医長 伊藤 友弥先生にお話を伺いました。
※本記事は2020年6月9日時点の医師個人の知見に基づくものです。
熱中症リスクー子どもが熱中症になりやすい理由
子どもは熱中症を引き起こしやすいといわれていますが、その理由を教えてください。また、乳幼児と児童で熱中症に注意すべきタイミングはそれぞれどのような場合でしょうか?
子どもが熱中症になりやすい理由は大きく三つあります。
まず一つ目は体格の特徴です。子どもは体重に対して体表面積が広いので、温度や湿度など環境の影響を受けやすいと考えられています。
二つ目は発汗の機能が弱いことです。子どもの発汗機能は成人ほど高くないため、体温を下げる能力が低く、体の中に熱がこもりやすいと考えられます。
三つ目は自分で適切な水分摂取ができないことです。乳幼児では喉の乾きを訴えることはできません。また児童でも自分で喉の乾きに気づくことが難しく、水分を摂取すべき場面で遊びや運動に夢中になってしまい適切な水分摂取を行いにくいということがあります。
乳幼児の場合、高温の環境下に長く置かれてしまうと熱中症になることがあります。たとえば、高温の車内で待たされるような状況です。一方で、小学生などの児童ではスポーツなどの運動をしている際に熱中症を発症することが多いです。
今年は新型コロナウイルスの影響から外出時のマスクの着用が求められていますが、マスクの着用によって熱中症のリスクは高まるのでしょうか?
マスクを着用すること自体が熱中症のリスクを高めるとは考えにくいです。マスクをしていることで水分摂取をしにくい、マスクがあることで顔付近の発汗機能が発揮されにくいなどはあるかもしれませんが、熱中症に対する影響は限定的だと考えます。一方で、運動時にもマスクを着用したり、人が少ない屋外でもマスクを着用し続けることは熱中症のリスクをあげる可能性はあります。 飛沫感染を防ぐために乳幼児にもマスクを着用させる親もいるようですが、マスクが気道を閉塞させて窒息させる恐れがあるので危険です。また、マスクをつけた状態でベビーカーなどで移動をする時には、本人の様子が観察しづらいこともあると思いますので、2歳未満のマスク着用は避けていただきたいです。
新型コロナウイルスの影響から外出を控えて自宅で過ごす子どもも多いと思います。このような状況下での熱中症のリスクについてはどのようにお考えでしょうか?
近年、直射日光に長時間浴びることで発症する熱中症を防ぐとともに室内での熱中症予防にも力が入れられています。特に一人暮らしの高齢の方が空調を使用せずにいた場合、室内でも熱中症を発症して時に重症となっていることが知られていると思います。
子どもの場合は屋内で熱中症にかかるリスクは低いと思われるものの、空調の効いた室内で過ごし水分摂取をしっかり行う必要はあると思います。
子どものなかでも特にどの年代での熱中症の発症が多いのでしょうか。また、熱中症を引き起こしやすい子どもの特徴には何が考えられるのでしょうか。
子どもの熱中症は男児に多く、特に小学校高学年のスポーツ時の発症が多いという特徴があります。多くは軽症(I度熱中症)で済み、涼しい場所で水分摂取をして休めば回復します。
このような場合に熱中症にかかる子どもが多い背景としては、屋外での遊びや部活動・スポーツ活動の際、適切な休息や水分摂取ができていないということが考えられます。そのため屋外で活動する際は適切な休息や水分摂取を子どもの判断に任せるのではなく、周りの大人たちから積極的にはたらきかける必要があります。
重症化リスクー体への影響とは
重症化のリスクに関しては、大人に比べてどの程度高いのでしょうか?
自ら喉が渇いていることを訴え、飲水ができる子どもであれば熱中症が重症化するリスクは大人とそう変わらないでしょう。
一方で、自ら飲水行動を取ることのできない乳幼児や医療的ケア児などはほかの子どもに比べて熱中症を発症するリスクが高いと思われるので注意する必要があります。
熱が異常に高くなると脳へ影響があるといった情報もありますが、熱中症が重症化した場合、ほかの臓器に影響を及ぼす、後遺症が残るなどはあるのでしょうか?子どもにはどのような影響があるのか教えてください。
熱中症はこむら返りや疲労感にとどまるI度熱中症から、頭痛や吐き気などが生じるⅡ度熱中症、熱射病といわれていた意識障害やけいれんなどが生じるⅢ度熱中症まで3段階に分類されています。
そのうち、自身の体温の調節機能が保たれているI・Ⅱ度熱中症については、適切な対応・処置を行えば後遺症を残すことは少ないと考えられます。
一方、Ⅲ度熱中症では体温の調節機能が破綻していますので、高体温によって体の機能を維持している酵素機能が崩れ、意識障害や多臓器不全となって生命の維持が困難になるケースや後遺症が残るケースもあります。
症状の特徴ー新型コロナウイルスとの違い
子どもがどういった症状を訴えている場合、またはどういった症状や行動がみられる場合に熱中症を疑えばよいでしょうか?子どもが出す熱中症のサインを軽症~重症度別に教えてください。
熱中症を疑う症状として、軽症(I度熱中症)であれば発汗、口渇感、尿の減少、こむら返りなどが挙げられます。一方、中等症(Ⅱ度熱中症)になれば頭痛や嘔吐、脈が速くなるなどの症状が現れる可能性があります。さらに、重症の熱中症(Ⅲ度熱中症)であれば意識障害(せん妄や失神など)やけいれんなどが現れます。
具体的な症状の訴えとしては、“喉が渇く”“気持ちが悪い”“頭が痛い”“足がつる”“フラフラする”“おしっこの色が濃い”などが挙げられます。特に気温の高い場所で長期間休息なく動き回っていた場合や、熱中症にかかりやすい環境に身を置いていた場合は注意が必要です。これらの症状がある場合には、まずは涼しいところで水分摂取をさせてゆっくり休ませましょう。
新型コロナウイルスと熱中症の症状は似ている点もあると思います。両者で異なるポイントや、どの程度の症状で受診を検討したほうがよいのか目安を教えてください。
新型コロナウイルスはウイルスによる感染症であるため、感染者との接触があり潜伏期間を経て咳や発熱、鼻水などの症状が現れます。一方で、熱中症は環境による障害であるため発症様式が異なります。高温多湿の環境で過ごしていて熱がある子どもが数時間の経過で症状が現れるようであれば、感染症よりも熱中症を疑うことが多いのではないでしょうか。
子どもの新型コロナウイルス感染症は軽症であることが多いといわれています。そのため、通常の風邪と同じように全身状態(呼吸の様子、食事や水分摂取の様子、睡眠の様子)などを数日間ほど観察し、気になる症状があれば受診を検討しましょう。
対処方法ー救急車を要請する目安
子どもに熱中症を疑う症状がある場合の応急処置方法を教えてください。また、医療機関を受診する、救急車を要請する基準を教えてください。
大量の発汗や疲労感などの症状であれば、空調の効いた室内や木陰などの涼しい場所で水分摂取をしながら経過を見てよいでしょう。しかし、休んでも汗が引かない、様子がおかしいなど改善の様子がなければ医療機関を受診しましょう。
なお、意識障害やけいれんなどの重症な症状が現れているようであれば直ちに救急車を要請しましょう。
夜間や旅行先などすぐに医療機関へ受診ができない状況で熱中症を疑う症状があった場合、どのような処置をすればよいか教えてください。
熱中症が生じるような環境に身を置いており、熱中症と考えられるような症状が現れている場合で適切な水分摂取などを行っていても症状が改善しないときには、夜間や旅行先でも迷わず医療機関を受診すべきです。
子どもの熱中症発症に備えて普段から用意しておいたほうがよいものなどはありますか。
熱中症は予防が可能な病気なので、まずは発症させないことが重要です。
熱中症対策としては、長時間にわたって高温・多湿の環境で遊んだり、スポーツをしたりすることを控えましょう。また、「喉が渇いた」と感じるときには軽度の脱水になっていることが考えられるため、喉が渇く前にこまめに水分摂取することを心がけましょう。
子どもがこれらの予防策を自ら率先して行うことは難しいため、大人から積極的に声かけをし、確実に休息や水分摂取をさせるようにしましょう。
医療機関では熱中症と診断された子どもに対して、どのような治療を行うのでしょうか。
医療機関に搬送されてくる熱中症の子どもに対しては、体を冷やすことによって体温を下げ、脱水を和らげる治療を行います。また、重症な熱中症の場合は全身の集中治療が必要ですので、集中治療室で呼吸や循環、体温の管理を行います。
熱中症対策ー暑さ対策の注意点
子どもと外出する際には、熱中症を防ぐため特にどのような点に注意するとよいでしょうか。新型コロナウイルスの影響から今年は外出時のマスクの着用が求められていますが、外の暑さから子どもを守る対策として工夫できるポイントなどを教えてください。
熱中症は予防が重要です。外出する際には出発の前に水分をしっかり取りましょう。
また、色の濃い服は太陽の光が吸収されやすく高温になるため、熱中症にかかるリスクを高めます。したがって、屋外に出るときは薄い色の服を着たり帽子をかぶったりして、直射日光による影響を小さくするように心がけましょう。
外出を控えたほうがよい目安などはありますか?
環境省などが提示している“暑さ指数(WBGT)”を目安にするとよいと思います。暑さ指数で“危険”“厳重警戒”となっているときは、運動や外出は控えましょう。
暑さ指数は以下のサイトで調べることができます。
【環境省】熱中症予防サイト“暑さ指数(WBGT)の実況と予測”
自宅(室内)の環境について、熱中症を防ぐために工夫できるポイントなどを教えてください。
空調の効いた環境で過ごすのがよいと思います。全ての部屋で空調が完備されていないようであれば、気温が上がる時間帯だけでも図書館などの涼しい場所で読書や勉強をするといった工夫をするとよいでしょう。
外出自粛による熱中症リスクにおいて工夫できるポイントはありますか?
自宅で普通に過ごしていれば熱中症になるリスクは低いと思います。水分摂取をこまめに行うほか、気温が高い日は空調をうまく活用しましょう。
適切な水分補給の仕方を教えてください。また、水分についてはお茶やジュースでもよいのでしょうか。
効率のよい水分の吸収には、塩分と糖分の両方がバランスよく含まれている必要があり、飲み物はイオン飲料などが望ましいといえます。水やお茶では喪失した塩分を補充することができません。また、ジュースでは糖分は含まれていますが塩分が含まれておらず、糖分は濃度が高いため大量に飲むと下痢を引き起こすこともあります。
また、イオン飲料がない場合でも自宅にある調味料で作成できるさまざまなレシピが公開されていますので、参考にして作ってみてもよいでしょう。
子どもの日頃の体調管理には特にどのような点で気をつけるとよいか教えてください。
規則正しい生活を心がけるのが第一だと思います。日中の活動をしっかり行うためにも、夜はよく眠り、食事を3食しっかり食べましょう。このような規則正しい生活が行えていないと、熱中症になるリスクも多少上がると考えられます。
熱中症対策で参考になる一般向けの情報源(サイト)などはありますでしょうか。
環境省のサイトは、熱中症について正しい情報を伝えています。
【環境省】熱中症予防情報サイト
また、日本小児科学会の“こども救急オンライン”も参考にされるとよいでしょう。
【日本小児科学会】こどもの救急(ONLINE QQ)
最後に、読者にメッセージをお願いいします。
熱中症の多くは予防が可能です。しかし、子どもは自分で体温調節・水分摂取を管理することが難しく、熱中症を防ぐためには大人がはたらきかける必要があります。
水分摂取や休息を子ども任せにするのではなく、一緒にいる大人が積極的に声をかけて子どもたちの熱中症を防ぎましょう。
関連記事
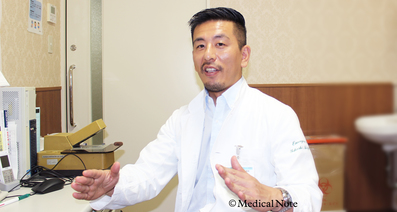

子どもの熱中症-自宅でできる処置・対処法とは?

子どもの熱中症の症状-「吐き気がする」「お腹が痛い」は熱中症のサイン?
関連の医療相談が21件あります
熱中症の後遺症?
2年前の夏に熱中症にかかりました。 数ヶ月くらいだるさがあったのですが治りました。 しかし、それから暑い場所に行くとフラフラしたり、気持ち悪くなったりする事が増えました。 熱中症の後遺症というのはあるのでしょうか?
熱中症、自律神経
8/17日頃食事もとらず、睡眠不足で、最高気温35度の中、日中暑い場所で長時間過ごし、水分も1口ほどしか取らず、夜頃目的地に向かい、涼しい場所に移動しようとした所、その場所が閉鎖されていたことを確認した瞬間、体が内から湧き出るように赤くなり、灼熱感に見舞われ熱中症で倒れてしまい、救急車を呼ぶか迷ったが、コンビニで氷と経口補水液、水、パンなどを買い、近くのトイレで氷を頭からかぶり、水分をとって、全身を1時間ほど冷やし続けた。なんとか意識を戻して家に帰り体を冷やしながら寝たが、部屋が暑かったため、朝起きた瞬間同じ症状に見舞われ、全身が赤くなり内から湧き出るような熱を感じた。外が暑くて外出出来なかったため朝頃病院へ行くと熱中症と診断され冷たい点滴を2500ml打った。次の日からも体の内部から赤いものが出て、それが20日程続いており、熱が下がらない状態。体温は脇から測るので、発症日から37℃程しか熱はなかったが、内部温度は非常に高い状態だった。その後も体調調節が効かず、部屋の温度が1℃上がるだけでも体が真っ赤になってしまったりする。体の深部温度を下げるためには冷たい点滴を打つしかないのでしょうか。サーモグラフィーを使って体の内部の温度を調べたり、改善に向かうしっかりとした治療を望んでいるのですがどうしたら良いのでしょうか。
最近頭痛がひどいです。
先週の土曜から体調が悪く、一昨日に受診して熱中症だと診断され点滴をやりました。 2日間自宅療養していたけど、症状がよくなりません。 まだ頭痛、眩暈、立ちくらみ、腹痛、下痢、手足や首の痛み、最近は幻聴があります。 明日、受診したときに血液検査と尿検査をして結果がでるのですが、他に考えられる病気ってありますか? 最近2ヶ月仕事のことで悩んでいるのですが、ストレスからも考えられますか?
脱水、夏バテや熱中症の対策、対応について。
夏場なのですが、仕事上、温度差があり、とても汗をかくことが多いです。 その際なのですが、両足に力が入りづらかったり 集中しないと意識が飛んでしまうような感覚。 ふらつき等が現れます。 対策として、スポーツドリンクをこまめに摂取する。 クーラーを付ける。(暑すぎるため) また、そういった症状が酷くなる前に休む。 等気をつけるようにしてるのですが、改善しづらく、どれかしらの症状が出ます。 より効果的に改善するにはどのようにすれば良いのでしょうか。 また、症状が出た時、適切な休み方等ありましたらお教え頂きたく相談させて頂きました。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「熱中症」を登録すると、新着の情報をお知らせします


















