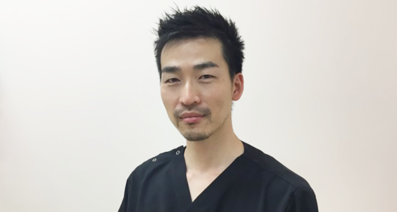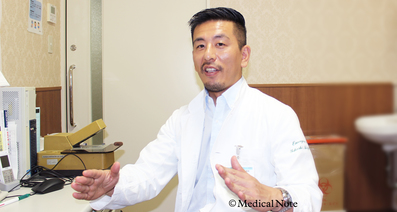
高齢者は熱中症にかかりやすく重症化しやすいといわれています。2010年のデータによれば、熱中症による死亡者(1,745人)のうち80%が65歳以上の高齢者であったといわれています。熱中症も死亡や障害が残る可能性が十分にある病気であることを今一度認識しましょう。
今回は高齢者が熱中症にかかりやすい理由や予防として本人や家族ができること、熱中症が疑われる症状が現れた場合の応急処置や病院の受診について、医療法人社団ときわ 赤羽在宅クリニック 小畑 正孝先生にお話を伺いました。
※本記事は2020年6月16日時点の医師個人の知見に基づくものです。
高齢者の熱中症リスク
熱中症にかかる人のおよそ半数以上が高齢者だといわれています。その理由にはどのようなことが考えられるのでしょうか?
高齢の方が熱中症にかかりやすい主な理由は、体温調節機能が低下していることや一般の方に比べて体の水分量が少ないことが挙げられます。体の水分量が少ないと、汗によって失った水分がたとえ少量であっても熱中症にかかりやすく、重症化しやすくなります。
高齢者のなかでも特に熱中症を引き起こしやすい人にはどのような特徴があるのでしょうか?
高齢の方のなかでも特に熱中症を引き起こしやすいと考えられるのは、一人暮らしの方、認知症にかかっている方、普段から活動的な方などです。
前述のとおり、一人暮らしの方の場合は孤立しやすく、外から見た症状の変化に気付いてくれる人がいません。また、高齢の方には熱くてもエアコンの使用を我慢される方や暑さに気付きにくい方もいるため、一人暮らしの場合は特に熱中症を引き起こしやすい環境に身を置いてしまう場合があると考えられます。
また、認知症を発症している方の場合も、自身では暑さや症状に気付きにくい傾向があります。さらに気温に対して適正な服装を身につけられなかったり、自分で室温をコントロールできなかったりするため、熱中症を引き起こすリスクが高まりやすいといえます。
なお、意外と思われるかもしれませんが、普段から活動的な方も熱中症になりやすいと考えられます。活動的な方は“自分は元気だから大丈夫”と過信し、必要な対策を怠ったり対処が遅れたりしてしまいがちです。そのため、どんな方でも対策を怠れば熱中症になるのだということを忘れずに過ごしてください。
熱中症を引き起こす要因の中でも、高齢者が特に注意すべき点を教えてください。
特に注意すべき点としては水分不足が挙げられます。そのため、夏の暑い時期は意識的にこまめな水分補給をするようにしましょう。
また、高齢になると気温を感じとる機能が低下するため、自分の感覚では暑くないと感じていても実際には熱中症になり得るような気温の中で過ごしていることがあります。したがって、暑さを体感で判断するのではなく温度計の数値を基準に判断し、エアコンをつけるなどの暑さ対策を行いましょう。
新型コロナウイルス感染症の影響による熱中症リスク
今年は新型コロナウイルス感染症の影響から外出時にはマスクの着用が求められています。マスクの着用によって熱中症のリスクは高まるのでしょうか?
マスクの着用によって通常時よりも熱中症のリスクは高まると考えます。これはマスクの中で熱がこもりやすくなるほか、マスクをすることによって呼吸回数が減り、呼気からの放熱がしにくくなるためです。
新型コロナウイルス感染症の影響から不要な外出は控えて自宅で過ごす高齢者もいると思います。このような状況下での熱中症のリスクについてはどのようにお考えでしょうか?
高齢の方が一人暮らしをしている場合では、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、予防の観点から来客や家族の訪問を控えているケースも多く、孤立しやすい状況にあります。そのため、熱中症などの体調不良があっても発見が遅れる可能性が懸念されます。
熱中症の原因のひとつである脱水は熱中症が生じる2~3日前から徐々に進行することもあります。本人が異変を感じた段階でほかの人に相談し、適切な対処をすれば熱中症を防ぐことができるのですが、本人が異変に気付かない場合は見過ごすことで熱中症に発展し、重症化する恐れがあるので注意が必要です。
重症化リスク
高齢者で重症化するリスクが高いのはどのような人でしょうか?
持病がある方や体力低下、低栄養などによる虚弱状態(フレイル)に陥っている方は熱中症が起きた際の回復力が弱いため、すぐに対処しなければ重症化するリスクがあります。また、一人暮らしの方や家族と暮らしていても一人で部屋にこもりがちな方など、発見が遅れやすい方も重症化するリスクがあるといえるでしょう。
なお、心不全などの持病を持っていて普段から水分の摂取制限をされている方もいます。このような方も水分を取ることを控えているため熱中症にかかりやすく、重症化するリスクも高いと考えられます。
重症化すると後遺症が残る、死亡するなどのことは考えられるのでしょうか?
熱中症は重症化すれば後遺症が残るほか、最悪の場合には命を落とす可能性があります。特に脳は高温によって損傷を受けやすく、熱中症が重症化すると脳機能に関する後遺症が残ることもあるほか、脱水症状によってその場で脳梗塞が起きることもあります。
さらに高齢の方の場合には、応急処置や治療によって熱中症自体は回復しても入院している間に体が弱ってしまい、寝たきりになってしまうことも考えられます。
熱中症を疑った場合の応急処置法
どのような症状がある場合、熱中症を疑うとよいでしょうか?救急車を呼ぶ、医療機関を受診するなど必要な判断基準を教えてください。
熱中症の前兆として、ふらふらする、顔が火照る、なんとなく体がだるいといった症状が挙げられます。これらの症状は熱中症以外のめまいや立ちくらみ、倦怠感と区別をつけることは困難です。そのため、気温が高い日や運動中などにこのような症状を感じたら熱中症を疑い、涼しい場所で休みながら水分補給をしましょう。
熱中症の諸症状が出た場合でも、意識障害がなければひとまず涼しいところに行って体を冷やし、水分補給をするなどの応急処置を実施しましょう。応急処置を継続することで症状が和らぎ、通常どおりに活動できるようになれば軽症の熱中症と考えられるため、医療機関を受診する必要はありません。ただし、応急処置を続けても症状が回復しなかったり、体温が下がらなかったりする場合には中等症~重症の熱中症を疑い、医療機関を受診しましょう。
なお、意識障害が出ている場合には重症の熱中症が疑われるため、直ちに救急車を呼びましょう。意識障害とは意識を失った場合のみを指すのではなく、もうろうとした状態で会話が成立しなくなる、真っすぐ歩けないといったような症状が出ている場合も含みます。また、救急車を待つ間にも体を冷やすなどして体温を下げるように処置を続けましょう。
熱中症を疑う症状があるときの具体的な応急処置方法を教えてください。
涼しい場所に移動して衣服を緩めたうえで、首や腋の下、足の付け根を冷やしてください。保冷剤などがあれば理想的ですが、外出時などで手に入らない場合には自動販売機などの冷たい飲み物を活用するとよいでしょう。
また、水分補給も大切です。熱中症の症状が現れている間の飲み物は可能であれば経口補水液やスポーツドリンクが望ましいでしょう。
新型コロナウイルス感染症と熱中症の症状では似ている点もあると思います。異なるポイントや症状がどの程度のときに受診を検討したほうがよいか、目安を教えてください。
新型コロナウイルス感染症と熱中症の鑑別では、外部環境が一番の判断基準となります。周りが高温である場合や湿度が高い場合には熱中症を疑ってください。ただし、意識障害や呼吸障害がなければ、焦って医療機関を受診する必要はありません。まずは涼しい場所で休ませ、水分補給を促しましょう。
夜間や旅行先など、すぐに医療機関へ受診ができない状況で熱中症を疑う症状があった場合、どのような処置をすればよいか教えてください。
意識障害がなければ医療機関の受診は不要です。前述の応急処置をし、涼しいところで休んで体力を回復させましょう。ただし、意識障害がある場合は早急に救急車を呼びましょう。
家族ができる熱中症対策
高齢者が熱中症を発症したときに備えて普段から用意しておいたほうがよいものなどはありますか?
自宅であれば保冷剤や経口補水液、スポーツドリンクを用意しておくとよいでしょう。ただし、経口補水液やスポーツドリンクは、高血圧や心不全などで塩分制限が必要な方が飲むと持病の悪化を招くこともあります。そのため、これらの持病をかかえている場合には緊急時に飲んでも大丈夫か、飲んでよい量はどのくらいかなどを事前に主治医に確認しておきましょう。
高齢者の家族や同居者は高齢者にどういった症状や行動が見られる場合に発症を疑えばよいでしょうか?
顔が赤い、体が熱い、多量の汗をかいている、暑いのにまったく汗をかいていない、ふらつく、転ぶ、話のつじつまが合わないなどがあれば熱中症を疑いましょう。特に室温の高い場所にいた場合には熱中症である可能性が高いと考えられます。
話のつじつまが合わないなどの症状が現れると認知症を疑うご家族もいますが、認知症は急に発症することはありません。急な変化があった場合には、何か体の異常が起きている可能性が高いと考えたほうがよいでしょう。
高齢者の熱中症対策として家族や同居者はどのような点に注意して高齢者をサポートすればよいでしょうか?
エアコンを嫌がる高齢の方は多いですが、暑い日には必ずエアコンを使うようにしましょう。前述のとおり、室温が25℃になったら使用を検討し、28℃以上になった場合には必ず使うようにしてください。
また、高齢の方は熱中症が重症化するリスクが高いため、早めの対処が重要です。普段と少しでも様子が違うことがあれば、水分補給や体を冷やすなどの対応を行いましょう。
外出時の熱中症対策
買い物、通院などで外出する際には熱中症を防ぐため特にどのような点に注意するとよいでしょうか?
まず、お昼の暑い時間帯は外出を避けるようにしましょう。やむを得ず外出する際には短時間で済むように工夫してください。
暑い時間帯の外出では直射日光を避けることも大切です。帽子や日傘を使い、さらになるべく日陰を歩くように心がけてください。また、首に巻ける保冷剤など継続的に体を冷やせる対策グッズは、熱中症予防として大変有効なのでぜひ活用してみてください。
マスクの着用による熱中症リスクにおいて工夫できるポイントはありますか?
1人で過ごしているとき、路上を歩いているときなど人が密集していない所では、マスクは外しても構いません。ただし、取り外しのときに手を汚染しやすいので必ず耳のひもを持ち、布部分には触れないよう取り扱いや保管に注意しましょう。
また、新型コロナウイルス感染症の影響からマスクの入手が困難であることもあり、使用済みのマスクを繰り返し使用している方もいます。しかし、使用済みのマスクはウイルスが付着している可能性もあるため、触ることによって感染のリスクが高まることが懸念されます。したがって、マスクの流通が戻り入手できるようになったら、一度外したマスクは捨て、都度新しいマスクを使うようにしてください。
熱中症を予防するため、外で行う散歩などは控えたほうがよいでしょうか?外出を控えたほうがよい目安などを教えてください。
適度な散歩・運動をすることは健康維持のうえで大切なことですが、炎天下の日や日中の外出は控えたほうがよいでしょう。やむを得ない理由による外出が必要な場合でも、体調が悪いときや寝不足のときは外出を控えることを推奨します。
室内での熱中症対策
外出自粛による熱中症リスクにおいて室内で工夫できるポイントはありますか?
熱中症予防には、室温などの環境管理や睡眠・食事などの体調管理はもちろん大切です。そのうえ一人暮らしの高齢の方などでは、外出自粛中でも孤立しないように電話やテレビ電話で誰かと連絡を取るようにしましょう。
部屋のエアコンをつける目安はどの程度でしょうか?
高齢の方が過ごす部屋では、室温が25℃を超えたときにエアコンの使用を検討し、28℃を超えたときには必ずエアコンをつけるようにしてください。高齢の方の中には、エアコンの使用を嫌う方もいます。しかし、前述のとおり高齢の方は体温調節機能が低下しているため、一般の方よりも暑さに弱いといえます。したがって、高齢の方が過ごす部屋では必要に応じて積極的にエアコンを活用しましょう。
また、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、エアコンの使用と換気の兼ね合いについて質問されることがあります。エアコンを使用している間は窓を閉め切ることが多く、換気が不十分になりやすいです。部屋に1人で過ごす分には、換気をしていなくても新型コロナウイルス感染症に感染するリスクが上がることはありませんので、特に換気を意識する必要はありません。しかし、1部屋に複数の方が過ごす場合には、エアコンをつけている間もこまめに換気する必要があります。換気の際は、エアコンをつけたまま室温をコントロールできる程度に窓を開けるか、しっかりと飛沫を取り除ける空気清浄機(具体的にはHEPAフィルターで部屋に見合った十分な流量のある空気清浄機)の使用を検討しましょう。
水分補給や食事のとり方
喉が渇いていなくても水分補給を行ったほうがよいのでしょうか?適切な水分補給の仕方を教えてください。
水分は喉が渇いていなくても飲んでください。目立った汗をかいていない場合でも、少なくとも1日1L程度は水分を取るように心がけましょう。特に高齢の方は喉が渇いても気付きにくく、一般の方と比べると脱水を起こす頻度が非常に高くなっています。
また、日常的な水分補給は水やお茶で構いません。たまに高齢の方の自宅に伺うと経口補水液を箱買いし日常的に飲んでいることがありますが、経口補水液やスポーツドリンクは日常的な水分補給の手段とするには塩分量が多く、飲み続けることによって塩分過多になる恐れがあります。特に心不全や高血圧などの持病のある方は注意が必要です。経口補水液やスポーツドリンクは大量に汗をかいたときや運動をしたとき、熱中症を疑う症状が現れたときのみ飲むようにしましょう。
夏の暑さから食欲が出ない場合は、無理に食べる必要があるのでしょうか?
まずは、寝不足やお酒の飲み過ぎに気を付けましょう。食事に関しては1日3食の栄養バランスの取れた食事を取ることが望ましいとされますが、夏バテで食欲が出ないときには量を減らす、あっさりしたものを食べるなどの工夫をして、食べられる分だけでも食べるように心がけましょう。食事をしないことにより体力が落ちると熱中症にかかりやすくなるため、まったく食べないようなことは避けてください。
熱中症情報
熱中症対策などで参考になる一般向けの情報源を教えてください。
環境省の熱中症予防情報サイトでは、熱中症の基本的な対策や予防、応急処置方法が閲覧できるほか、暑さ指数が確認できます。暑さ指数とは、熱中症を予防することを目的に提案された指標で、その日の熱中症の危険度を判断することができます。
【環境省】熱中症予防情報サイト
最後に、読者にメッセージをお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症や熱中症など、現在話題になっている病気に対して個別に予防していくことが大切です。しかし、もっと重要なことは、日頃から適度な運動をすることやしっかり寝て寝不足にならないこと、バランスのよい食生活をすることなど、常に自分の健康を気にかけ行動することです。
また、今回は熱中症対策と新型コロナウイルス感染症予防の兼ね合いも含めてお話しました。新型コロナウイルス感染症について危機感を持つ方は多いのですが、熱中症はよくある病気と思われているせいか軽視してしまう方もいます。しかし、年によって変動あるものの熱中症の死亡者は年間1,000人弱といわれており、そのうちの約8割は65歳以上の高齢の方です。救急搬送件数は5万件を超え、受診者は約30万件となっています。熱中症も死亡や障害が残る可能性が十分にある病気であることを今一度認識しましょう。
最後に、熱中症は新型コロナウイルス感染症のようにロックダウンなどをしなくても、一人ひとりが体調管理に注意すれば防げる病気です。しっかりと対策して夏を乗り切りましょう。
医療法人社団ときわ 理事長、医療法人社団ときわ 赤羽在宅クリニック 院長
小畑 正孝 先生2008年、東京大学医学部卒業。卒業後の2年間の研修医生活のなかで多くの矛盾や課題を発見したことがきっかけで、初期臨床研修終了後は医療制度・政策を研究するためすぐに東京大学大学院に進学し、公衆衛生学を学ぶ。在宅医療には大学院生時代のアルバイトから携わる。医療の矛盾や課題は、在宅医療という形でも解決できると考え、以後、在宅医療を専門とする診療所で院長として診療に従事。約300名の主治医として、患者さんに寄り添った診療を提供。より質の高い在宅医療を多くの方に提供するため、2016年9月に在宅医療を専門とする「赤羽在宅クリニック」を開業し、日々診療に邁進している。
小畑 正孝 先生の所属医療機関
関連記事
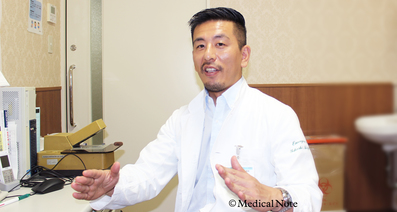

子どもの熱中症-自宅でできる処置・対処法とは?

子どもの熱中症の症状-「吐き気がする」「お腹が痛い」は熱中症のサイン?
関連の医療相談が21件あります
熱中症の後遺症?
2年前の夏に熱中症にかかりました。 数ヶ月くらいだるさがあったのですが治りました。 しかし、それから暑い場所に行くとフラフラしたり、気持ち悪くなったりする事が増えました。 熱中症の後遺症というのはあるのでしょうか?
熱中症、自律神経
8/17日頃食事もとらず、睡眠不足で、最高気温35度の中、日中暑い場所で長時間過ごし、水分も1口ほどしか取らず、夜頃目的地に向かい、涼しい場所に移動しようとした所、その場所が閉鎖されていたことを確認した瞬間、体が内から湧き出るように赤くなり、灼熱感に見舞われ熱中症で倒れてしまい、救急車を呼ぶか迷ったが、コンビニで氷と経口補水液、水、パンなどを買い、近くのトイレで氷を頭からかぶり、水分をとって、全身を1時間ほど冷やし続けた。なんとか意識を戻して家に帰り体を冷やしながら寝たが、部屋が暑かったため、朝起きた瞬間同じ症状に見舞われ、全身が赤くなり内から湧き出るような熱を感じた。外が暑くて外出出来なかったため朝頃病院へ行くと熱中症と診断され冷たい点滴を2500ml打った。次の日からも体の内部から赤いものが出て、それが20日程続いており、熱が下がらない状態。体温は脇から測るので、発症日から37℃程しか熱はなかったが、内部温度は非常に高い状態だった。その後も体調調節が効かず、部屋の温度が1℃上がるだけでも体が真っ赤になってしまったりする。体の深部温度を下げるためには冷たい点滴を打つしかないのでしょうか。サーモグラフィーを使って体の内部の温度を調べたり、改善に向かうしっかりとした治療を望んでいるのですがどうしたら良いのでしょうか。
最近頭痛がひどいです。
先週の土曜から体調が悪く、一昨日に受診して熱中症だと診断され点滴をやりました。 2日間自宅療養していたけど、症状がよくなりません。 まだ頭痛、眩暈、立ちくらみ、腹痛、下痢、手足や首の痛み、最近は幻聴があります。 明日、受診したときに血液検査と尿検査をして結果がでるのですが、他に考えられる病気ってありますか? 最近2ヶ月仕事のことで悩んでいるのですが、ストレスからも考えられますか?
脱水、夏バテや熱中症の対策、対応について。
夏場なのですが、仕事上、温度差があり、とても汗をかくことが多いです。 その際なのですが、両足に力が入りづらかったり 集中しないと意識が飛んでしまうような感覚。 ふらつき等が現れます。 対策として、スポーツドリンクをこまめに摂取する。 クーラーを付ける。(暑すぎるため) また、そういった症状が酷くなる前に休む。 等気をつけるようにしてるのですが、改善しづらく、どれかしらの症状が出ます。 より効果的に改善するにはどのようにすれば良いのでしょうか。 また、症状が出た時、適切な休み方等ありましたらお教え頂きたく相談させて頂きました。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「熱中症」を登録すると、新着の情報をお知らせします